シンポジウム参加費
一般: 5000円(事前振込),7000円(当日払い)
学生: 2000円(事前振込),3000円(当日払い)
懇親会費(事前振込,当日払いともに)
一般: 5000円
学生: 2000円
事前振込のための参加登録の受付は終了しました.
ご協力どうもありがとうございました.
事前登録なしでの参加も可能です.
その場合,当日受付にて参加費(当日払い)をお支払い下さい.
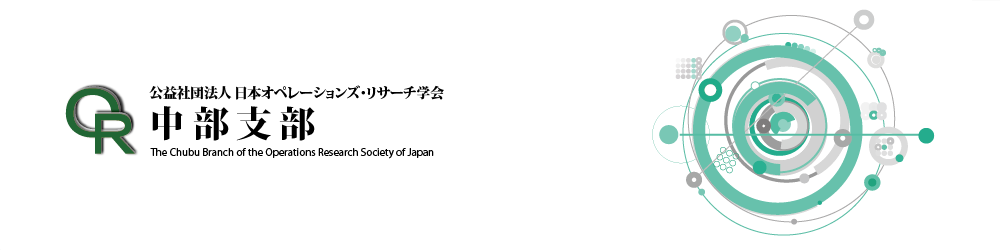
シンポジウム参加費
一般: 5000円(事前振込),7000円(当日払い)
学生: 2000円(事前振込),3000円(当日払い)
懇親会費(事前振込,当日払いともに)
一般: 5000円
学生: 2000円
事前振込のための参加登録の受付は終了しました.
ご協力どうもありがとうございました.
事前登録なしでの参加も可能です.
その場合,当日受付にて参加費(当日払い)をお支払い下さい.
第22回RAMPシンポジウム実行委員会
問い合わせ先
事務局: 〒464-8603 名古屋市千種区不老町
名古屋大学大学院工学研究科機械理工学専攻
田地宏一
r a m p 2 0 1 0 “at” al.cm.is.nagoya-u.ac.jp
OR学会中部支部の会員の皆様
下記の通り,来年3月13日に第37回中部支部研究発表会を開催致します.発表申し込みは2010年1月22日(金)までとなっております.是非ご検討ください.
■研究発表会の日程・会場
日時: 2010年3月13日 (土) 14:40-18:00(予定)
会場: 中部品質管理協会第1研修室
名古屋市中村区名駅四丁目10番27号(第2豊田ビル西館8階)
#特別講演(13:30~14:30)が決まりました
演題:「研究と学会活動を巡るランダムウォーク」
講師:伏見正則先生(南山大学情報理工学)
■■重要日程■■
発表申し込み:2010年1月22日 (金)
発表原稿提出:2010年2月26日 (金)
以下に発表申し込みと原稿提出について明記します.
—
■発表申し込み [申し込み締切: 2010年1月22日 (金)]
発表をご希望される方は,
1) 発表題目
2) 著者氏名と所属
3) 発表者氏名
4) 連絡先 E-mailアドレス
を,件名を「第37回中部支部研究発表会申し込み」として,
chubu.or.conference[at]gmail.com
宛てのE-mailでお知らせください.
#発表時間は,おおむね質疑応答を含めて約15-20分を予定しております.
■発表資格について
論文著者(ファーストオーサー,連名者)のいずれかがOR学会会員であること.
■発表原稿書式
発表原稿は下記の書式に従って用意して下さい.
・A4サイズ4ページ以内,天地左右のマージン各20mm以上.
・題名の後に,氏名,所属,住所,E-mailアドレスを記載.
■発表原稿の送付 [提出締切: 2010年2月26日 (金)]
発表原稿を PDF ファイルで,下記送付先までE-mailでお送り下さい.PDFファイルを作成する際には,以下の点にご注意下さい.
・使用したフォントは全て埋め込んで下さい.
・ファイルサイズはおおむね1MB以下にして下さい.
■ 申し込み・原稿送付先(問い合わせ先と違います)
OR学会中部支部研究会 <chubu.or.conference[at]gmail.com>
—
■ 問い合わせ先
奥田隆史
愛知県立大学 情報科学部 情報科学科
〒480-1198 愛知郡長久手町大字熊張字茨ヶ廻間1522-3
Tel: 0561-64-1111 内線 3404
Fax: 0561-64-1108
E-mail: okuda[at]ist.aichi-pu.ac.jp,
========
シンポジウム会場: 名古屋大学・東山キャンパス 豊田講堂 シンポジオンホール
〒464-8601 名古屋市千種区不老町
地下鉄名城線 名古屋大学駅 2番出口から徒歩3分
懇親会場: 名古屋大学・東山キャンパス レストラン花の木
1. 原稿
原稿は,RAMP2010のウェブサイトにアップロードされたLaTeXもしくはMicrosoft Wordのスタイルファイルを用いて,日本語もしくは英語で作成すること.総ページ数は15ページ以下であることが好ましい.なお,本ファイルは,フォントサイズは12ポイントであり,ページ番号は付与されない.
2. 締切
原稿の投稿期限は2010年8月23日(月)とする.原稿は,pdfファイルの形式に変換し,
ramp2010[at]al.cm.is.nagoya-u.ac.jp
宛てに電子メールで投稿すること.なお,LaTeXおよびMS-Wordのスタイルファイルは本ページより入手できる.
LaTeX >> スタイルファイル サンプル (PDF)
MS-Word (Windows) >> スタイルファイル サンプル (PDF)
3. タイトルページ
タイトルページには以下の情報を含めること
1. 原稿のタイトル
2. 著者,所属,メールアドレス
3. 概要(英語の場合200語以内,日本語の場合500字以内)
4. キーワード
4. 数式
ディスプレイ形式の数式で参照番号が必要な場合は, (1)もしくは(1.1)のような形で右側に付記すること.
5. 図表
図表は連続した番号を付け,タイトルも一目見て内容が理解できるような分かり易いものにする.また,これらは文末にまとめて置くのではなく,適宜,文中に挿入すること.
6. 参考文献
参考文献を書く際には,以下のことに注意すること.
* 第一著者がアルファベット順で並ぶようにする.
* 各文献には数字で番号を振り,文中で参照する際は番号を大括弧で括って表記する.
* 論文誌の名前は略称ではなく,フルスペルを用いる.
各文献の具体的な書き方として,論文を集めた本ならば文献[1]のように,学術誌ならば文献[2]のように,書籍(単行本)ならば文献[3]のようにする.
7. 著作権
第22回RAMPシンポジウム論文集に記載された論文の著作権は,すべて日本オペレーションズリサーチ学会に属するものとする.
8. フォント (Microsoft Word)
Windows版の場合はCentury, Symbol, MS 明朝のいずれかを用いること.
参考文献
[1] S. Fujishige: Linear and nonlinear optimization problems with submodular constraints, In M. Iri and K. Tanabe (eds.), Mathematical Programming – Recent Development and Applications (KTK Scientific Publishers, Tokyo, 1989), 203-225. [2] H. Konno: Piecewise linear risk functions and portfolio optimization, Journal of the Operations Research Society of Japan 33 (1990), 139-156. [3] M. Fukushima: Introduction to Mathematical Programming (Japanese), (Asakura Shoten, Tokyo, 1996).12月12日(土)13時30分から中部品質管理協会において,平成21年度支部講演会が開催されました.
第1件目の講演は,八卷 直一(静岡大学 情報基盤機構,情報学部)先生による
「幕末から明治へ ~ そしてORの未来へ ~」
で,何人かの仕事を成した人の紹介から始まりました.
そして,ついにOR学会から首相を輩出した点に触れ,会員の研究交流・学会として社会貢献の重要性を説かれました.今こそ科学を社会のために何かできないかという先生の意志を感じました.
時折ご趣味の鉄道の話を挟みながら,ORに携わってきた経験を約1時間お話くださいました.
第2件目の講演は,腰塚 武志(南山大学 情報理工学部情報システム数理学科)先生の
「積分幾何学に関わって」
でした.内容をいくつか掻い摘んでみますと,
下記のように,支部講演会と忘年会を開催いたします.ふるってご参加頂きたくお願い申し上げます.
忘年会は講演会終了後に開催いたします.当日申し込みも可能ですが,予約の都合上出来る限り事前に申し込んでいただければ幸いです.
支部講演会
日時:平成21年12月12日(土)13時30分~16時30分
場所:中部品質管理協会
〒450-0002 名古屋市中村区名駅四丁目10番27号
第2豊田ビル西館8階 (所在地地図)
————————————–
1.講演者: 八卷 直一 ( 静岡大学 情報基盤機構,情報学部 )
題目: 幕末から明治へ ~ そしてORの未来へ ~
講演概要: ペリーの来航から日露戦争へ日本の技術進歩はめざましいものがありました。しかし、一方で現在に至るまで存在する自虐意識も芽生えてしまったようです。この現象を鉄道技術史から垣間見て、ORのこれからを考えてみたいです。一方で、ペリーや日本のインテリの行動も参考に、システム思考の大切さを考えてみたいと思います。2.講演者: 腰塚 武志 ( 南山大学 情報理工学部情報システム数理学科 )
題目: 積分幾何学に関わって
講演概要:
・積分幾何学との出会い(一様な直線とは何か)
・道路網と交差点
・都市空間における距離分布,通過量分布
・一様な直線を介して4次元を2次元に
支部忘年会
日時:平成21年12月12日(土)17時~19時
場所:バーゴラ
会費:6千円
事前申し込み先:中部品質管理協会 安田 様 yasuda[at]cjqca.com
【OR学会中部支部ワークショップ】
ORの手法を用いて実際の問題を解決するためには,ソフトウェアの利用が不可欠です.OR学会中部支部では,ソフトウェアを利用して問題解決を行うためのワークショップを企画しました.このワークショップでは,ORのソフトウェアを開発,もしくは導入支援を行っている,高い技術力を持つソフトウェアベンダー各社の専門家に,問題解決のためのソフトウェアの実際問題への適用事例を紹介してもらいます.ワークショップ会場には,参加者1人に1台ずつノートPCを用意しています.そこで,ソフトウェアを利用して例題を解いて,現場での問題解決に役立ててもらえるようにします.企業の現場で問題解決に取組んでいる実務家,大学,大学院でオペレーションズ・リサーチを学んでいる学生の皆さんなど,多くの方に参加を歓迎します.
[日時] 2009年(平成21年)11月20日(金)13:00-18:00
[場所] 中部品質管理協会 セミナー室
〒450-0002 名古屋市中村区名駅四丁目10番27号
第2豊田ビル西館8階 (所在地地図)
[プログラムと講演概要]
■13:00-13:05 ワークショップ開催について
OR学会中部支部長 名古屋工業大学 大鑄 史男 教授
■13:05-14:35 SaaSによるロジスティックス最適化
(株)サイテック・ジャパン 伊倉 義郎 氏
SaaSを使ったロジスティックスの最適化について解説する。インターネットにより、いつでもどこからでもアクセスが出来るSaaSは現在急速にその活用が進んでいる。ロジスティックス・アプリケーションもSaaSによる利用が広がれば、大幅にその効果が拡大する可能性がある。ここでは、ロジ最適化の典型例ともいえる配車問題を、実際の配車SaaSサービス、WebSTARSを使って解決する方法について実演を交えながら解説する。
特に、この講演では配車がSaaSで簡単に行えることを示すため、実例をリアルタイムに解くことを試みる。そのために参加者には実際の配車問題例をExcelシートに準備をして当日講演に持参することを提案する。作成する問題のデータとしては、注文一覧と届け先住所の一覧であるが、それらのデータ形式と意味については、下記サイト(ページ中央の「配車データ」というリンクからダウンロード、pwd: webstars)の資料に記載されている。
http://www.saitech-inc.com
その他、実例も含めSaaSによるロジ最適化の可能性を紹介する。■14:45-16:15 Visual SLAMを用いたシミュレーション
(株)構造計画研究所 指尾 健太郎 氏
Visual SLAMは米 Purdue大学のPritsker教授が開発した汎用シミュレーション言語です。昨今のシミュレータが物流や生産システム等に機能を絞っている中、対象を選ばずに幅広いシミュレーションが可能です。また、長い間世界中で多くの人に使用されてきたツールであり、シミュレーション対象システムが時間変化やイベントの発生に応じて変化する様子を、視覚的にモデル化でき、非常に高速に実行できる実践的なツールです。また、シミュレーション教育のためのツールとして教育・研究機関等にも幅広く導入されています。
ここでは、Visual SLAMの機能と特徴について概説します。更に、例題として簡単な問題を想定し、Visual SLAMを用いたシミュレーションモデルの開発、実行、結果の確認と改善策の検討までの一連の問題解決手順を体験して頂きます。■16:25-17:55 体験、データマイニング!
~Visual Mining Studioハンズオンセミナー~
(株)数理システム 中江 俊博
Visual Mining Studioは(株)数理システムが開発した、国産初の本格的汎用データマイニングソフトウェアです。ビジュアルプログラミング環境を備えており、プログラムコードを書かなくても、アイコンのドラッグ&ドロップ、ダイアログ指定により、データの導入、加工から、分析までの一連の流れを作成することができますので、初心者でも手軽にデータ解析、データマイニング作業を行うことができます。取り組みやすいインターフェースのため、学部学生の方や、Excelは使うことができるのだけれど、もう少し深い分析がしたいというビジネスマンの方にも興味を持って本格的なデータマイニングに挑戦していただくことが可能です。マーケティングや品質管理、情報工学のみならず、教育用としての導入実績もあります。当日は実際にソフトを操作していただきながら、多彩な機能をご紹介します。Visual Mining Studioのトライアル版をお持ち帰りになり、ご自身のデータでお試しいただくことも可能です。■17:55-18:00 ワークショップのまとめ
OR学会中部支部 南山大学 鈴木 敦夫 教授[参加申し込み]
OR学会中部支部事務局(中部品質管理協会内)安田 (yasuda[at]cjqca.com)宛 電子メールでお申し込みください.会場の関係で参加者は30名とさせていただきます.
 2009年9月7日(月)に第二豊田ビル西館8階第1会議室におきまして,第6回日本OR 学会中部支部シンポジウム「情報化時代の情報通信システムの性能評価」が無事終了しましたことを報告いたします.
2009年9月7日(月)に第二豊田ビル西館8階第1会議室におきまして,第6回日本OR 学会中部支部シンポジウム「情報化時代の情報通信システムの性能評価」が無事終了しましたことを報告いたします.
今回も非常に盛況なシンポジウムとなり,会場は椅子が運び込まれるほどでした(参加者は全部で70名.そのうち学生が約半数の37名).この満席の会場の中,4人の講師の方々の興味深いお話しを聴くことができ,大変貴重な時間を過ごせました.そのあとは十数名で懇親会に場を移し,講師の方々とさらに交流を深めました.
今回のご講演は以下の4件でした.
(1) インターネットの将来に関する研究動向
国立情報学研究所 山田茂樹教授
(2) 情報通信ネットワークの性能評価に対する待ち行列理論
東京農工大学大学院 川島幸之助教授
(3) 情報システムにおけるシミュレーションの歩みと今後の可能性
(株)情報工房 多田正浩 代表取締役社長
(4) 社会システムの性能評価:マルチエージェントシミュレーション手法を利用して
(株)構造計画研究所 服部正太 代表取締役社長
情報通信システムという軸を立てたところに,待ち行列の基礎理論から,最近の話題,そしてシミュレーションの応用まで,お話しが幅広くセッティングされており,コーディネーターの奥田先生の意図がはっきりとしていて,よく練りこまれたプログラムだったという印象をうけました.
来年度も中部支部ではシンポジウムの企画を進めております.大学等の研究者・学生のみなさまから企業の実務者のみなさままでぜひご参加ください.
2009年 9月7日(月)に第6回日本OR 学会中部支部シンポジウム「情報化時代の情報通信システムの性能評価」を開催いたします.
■ 日時
2009 年9 月7 日(月)13:10-16:50
■ 場所
第二豊田ビル西館8階第1会議室
〒450-0002 名古屋市中村区名駅四丁目10番27号
<シンポジウム会場への地図 >
■ シンポジウム趣旨
情報通信システムは,我々の経済,文化,生活にまで大きな影響を与えてきました.さらに,第4 世代携帯電話,放送・通信の融合,ディジタルテレビル放送への移行などが計画されています.そのため,待ち行列理論,通信トラヒック理論,トラヒック・エンジニアリング,ネットワークシミュレーション,エージェントシミュレーションなどのOR 的な性能評価手法が活用される場面が拡大しています.本シンポジウムでは情報通信とOR の学際領域で活躍されている4 名の講師によるシンポジウムを企画しました.
皆様,奮ってご参加ください.
■ プログラム
(1) インターネットの将来に関する研究動向
国立情報学研究所 山田茂樹教授
(2) 情報通信ネットワークの性能評価に対する待ち行列理論
東京農工大学大学院 川島幸之助教授
(3) 情報システムにおけるシミュレーションの歩みと今後の可能性
(株)情報工房 多田正浩 代表取締役社長
(4) 社会システムの性能評価:マルチエージェントシミュレーション手法を利用して
(株)構造計画研究所 服部正太 代表取締役社長
■ 参加費(当日払い)
1,000 円(学生は無料)
■ 問い合わせ先
愛知県立大学・情報科学部 奥田隆史
電子メール:okuda[at]ist.aichi-pu.ac.jp
℡:0561-64-1111(内線3404)FAX:0561-64-1108
■ 後援・協賛団体
共催:中部OR研究会
協賛:(社)日本OR学会「待ち行列研究部会」,(社)電子情報通信学会東海支部,
(社)電気学会東海支部,(社)情報処理学会東海支部,
(社)日本品質管理学会中部支部,(社)日本経営工学会中部支部,
(財)日本規格協会 名古屋支部,中部品質管理協会
後援:(社)中部産業連盟
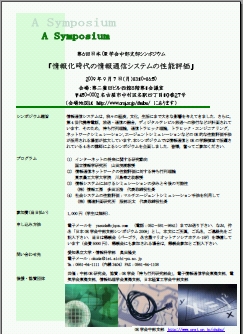
↑クリックするとポスターのPDFファイルが開きます(600KB)