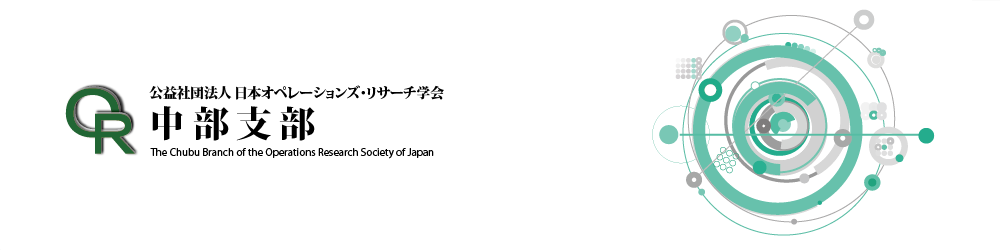【Update】懇親会会場を記載しました(2017/05/20)
OR学会中部支部 2017年度第1回支部講演会
日時:2017年6月17日(土)14:30-17:00
場所:愛知大学・名古屋キャンパス・808号室
〒453-8777 名古屋市中村区平池町4-60-6
http://www.aichi-u.ac.jp/profile/campus-nagoya.html
使用言語:英語
講演1(14:30-15:45)
Multi-State Network Reliability Evaluation
Ming J Zuo, University of Alberta, Canada
ABSTRACT:A multi-state network under consideration consists of a source node, a sink node, and some independent failure prone components in between. The components can work at different levels of capacity. For such a network, we are interested in evaluating the probability that the flow from the source node to the sink node is equal to or greater than a demanded flow of d units. A general method for reliability evaluation of such multi-state networks is using minimal path (cut) vectors. A minimal path vector to system state d is called a d-MP. The reliability of such a network can be defined as the probability of the component state vector being not smaller than at least one of the d-MPs. Efficient evaluation of the reliability of such a network is essential for its reliability assurance. In this presentation, we report our recent progress in improving algorithms for efficient evaluation of network reliability. These include methods for generating minimal path sets for binary network, generating d-MPs for multi-state networks, and network reliability evaluation using the sum of disjoint products approach and the state space decomposition approach.
講演2(15:45-17:00)
Heuristics for 2D and 3D packing problems
Yannan HU, University of Nagoya, Aichi
ABSTRACT:Two-dimensional and three dimensional packing problems belong to a class of combinatorial optimization problems. These problems are related to real-world applications and they have been studied for a long time from both theoretical and practical points of view. In a packing problem, it involves packing a set of objects, called items, into containers. The objective is to pack all the items without overlap into containers as densely as possible. Packing problems are known as NP-hard and a series of heuristics have been developed. This speech introduces some typical heuristics for these problems. There are many variations for the objective functions such as to pack a single container as densely as possible or to pack all items into as few container as possible.
For the two-dimensional packing problem, we consider the strip packing problem that has been intensively investigate. In a two-dimensional strip packing problem, we are given only a single rectangular container, called strip, whose width is fixed and height is unrestricted, and the objective is to minimize the height of the strip. We focus on packing items having two-dimensional shapes such as rectangles, rectilinear block or arbitrarily shaped polygons represented in bitmap format. A rectilinear block is a polygonal block whose interior angles are either 90 degrees or 270 degrees. These problems have applications in the wood, glass, and leather industries as well as LSI and VLSI design and newspaper paging.
For the three-dimensional packing problem, we focus on the problem in which cuboid items and containers are given and the task is to pack all the items into as few containers as possible. This problem is also called container loading problem. This type of problem appears in various industrial applications and becomes one of the critical problems to reduce the cost of logistics and transportation.
懇親会(会場周辺,会費5000円)18:00~
アサヒビアレストランスーパードライ 名古屋
〒450-0003 愛知県名古屋市中村区名駅南1-17-23 ニッタビルB1
懇親会に参加される方は、以下の申し込みフォームより、2017年6月10日までに入力をお願いします.
連絡先
愛知県立大学 奥田隆史 okuda○ist.aichi-pu.ac.jp
「アサヒビアレストランスーパードライ 名古屋」を12名で予約しました. 〒450-0003 愛知県名古屋市中村区名駅南1-17-23 ニッタビルB1