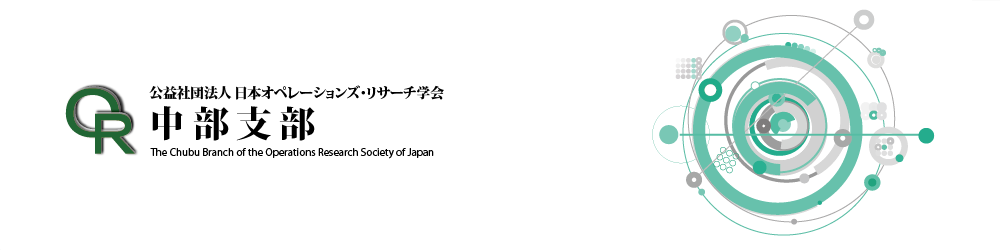<内容>
1.第5回日本OR学会中部支部シンポジウム
「インターネット時代のゲーム理論」
2008年9月5日(金)13:10-16:50,第二豊田ビル(西館)8階第1会議室
————————————————————————
1.第5回日本OR学会中部支部シンポジウムのご案内
ゲーム理論は従来,経済学的・経営的なモデルを分析するために主に用いられてきましたが,現在では,行動科学,政治学,生物学,論理学などの幅広い学問分野においても重要な分析手法として位置付けられています.特に近年におけるインターネットの普及によって,ネットワーク・ルーティングやインターネット・オークションなどをゲーム的状況として捉えた研究も盛んに行なわれるようになり,ゲーム理論と情報科学との関連が注目を集めています.
本シンポジウムではゲーム理論と情報科学との学際領域で活躍する研究者に講演してきただき,この研究分野における最新の成果を分かりやすく解説していただくとともに,この研究分野のさらなる発展に寄与することを目的とします.新しい時代におけるゲーム理論に関心を寄せる多くの皆様方のご参加をお待ち申し上げております.
主催 :日本オペレーションズ・リサーチ学会中部支部
共催 :中部OR研究会
協賛 :日本経営工学会中部支部,中部品質管理協会,日本品質管理学会中部支部
後援 :社団法人中部産業連盟
日時 :2008年9月5日(金)13:10-16:50
会場 :第二豊田ビル(西館)8階第1会議室(愛知県名古屋市)
参加費 :無料
お申し込み :シンポジウムへの当日受付は可能ですが,参加人数把握のため,出来る限り事前に申し込みをお願いします.下記問い合わせ先まで E-mail でお申し込み下さい.
懇親会 :シンポジウム終了後に懇親会を開催致します。懇親会は,会場予約の都合上,事前申し込みとさせて頂きます. 2008年8月31日(日)までに,下記問い合わせ先までE-mail でお申し込み下さい.
*詳細は,Webページ をご覧下さい.
プログラム
■ 13:10-13:15 開会挨拶
■ 13:15-14:00 講演1「無秩序の代償(price of anarchy)の理論入門」伊藤大雄氏(京都大学)
■ 14:10-14:55 講演2「ナッシュ均衡計算の複雑さ」岡本吉央氏(東京工業大学)
■ 15:05-15:50 講演3「インターネットオークションの理論(基礎)」渡辺隆裕氏(首都大学東京)
■ 16:00-16:45 講演4「インターネットオークションの理論(応用)」横尾真氏(九州大学)
■ 16:45-16:50 閉会挨拶
お問い合わせ
静岡大学工学部 安藤和敏
TEL/FAX: 053-478-1263,E-mail: ando[at]sys.eng.shizuoka.ac.jp