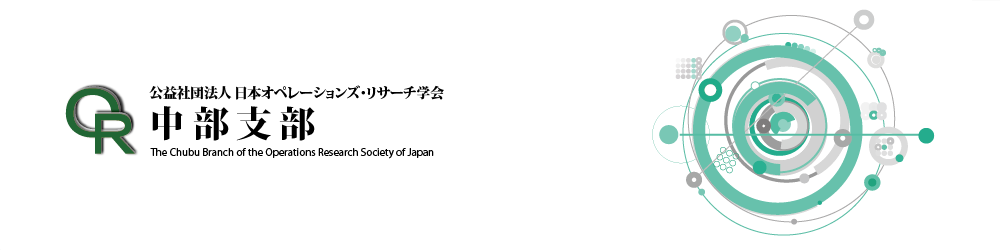2015年9月19日(土)に、ウインクあいちの愛知県立大学サテライトキャンパスにおいて、第12回OR学会中部支部シンポジウムが「航空機の保全設計技術とOR」をテーマに、35名の参加者を迎えて開催された。中部地区は「アジアNo.1航空宇宙産業クラスター形成特区」であり、日本の航空機・部品生産額の約5割、航空機体部品では7割以上を生産している。本シンポジウムでは航空産業で、国際競争の最前線で発展していける技術分野として複合材をテーマに3名の講師に、航空機に複合材がどのように適用されてきたか、また最新の複合材の紹介、これらの保全設計はどのようになされているか、オペレーションズ・リサーチとの関連を踏まえた保全方策について、ご講演をいただいた。
一人目の講演者の伊牟田 守 氏(岐阜県研究開発財団)は、「航空機における複合材料の適用と課題」
二人目の講演者の馬場 俊一 氏(サンワトレーディング株式会社 代表取締役)は、「連続繊維熱可塑材料(CFRTP,GFRTP)の成形法と用途」
三人目の講演者の伊藤 弘道 氏(金城学院大学 消費生活科学研究所)は、「民間航空機の保全や設計に関するORモデル」
一人目の講演者の伊牟田 守 氏(岐阜県研究開発財団)は、航空機用複合素材とは何か、その適用動向について、解説をいただいた。複合材料とは2種以上の素材を人為的に組み合わせて、もとの素材よりも優れた性質または新しい性質をもつように創造された材料である。これは繊維に樹脂を含浸させた半硬化状態の材料形態からオートクレーブという方法(加熱や加圧)を行うことにより成形され、航空機の胴体や主翼に適用される。その性質について、重さは鉄の4分の1、強度は鉄の10倍あり、燃えにくく耐熱性もある。その他、航空機に最適な性質として良好な耐食性(客室内湿度の増加)や高い疲労強度(整備間隔の延長(従来比2倍))があることのことだった。一方、この複合材料の適用拡大のための課題の一つとして信頼性向上が挙げられていた。複合材料は衝撃があった場合、一見、損傷がないようにみえても、内部で損傷していることがあり、目視の点検では困難である。そこで、超音波非破壊検査や光ファイバ等のセンサを神経系として複合材料に埋め込み、自己の健康状態を診断する技術が紹介された。これらの検査について点検間隔や診断間隔などオペレーションズ・リサーチ(OR)との関連を踏まえた保全方策の提案ができるのではと感じた。
二人目の講演者の馬場 俊一 氏(サンワトレーディング株式会社 代表取締役)は、複合材料の具体的な事例について解説された。1番目の講演で解説されたように複合材料とは、繊維に樹脂を含浸させた半硬化状態の材料から成形されるが、そこで使われる樹脂は2種類存在し、熱硬化性樹脂と熱可塑性樹脂とある。それぞれ製造工程における利点・欠点が存在し、主に前者は成形温度が低く、複雑な成形が可能であるが、成形サイクルが長く、冷凍保管が必要であり、後者は成形サイクルが60秒という短さで、常温で保管できるが、成形温度が高く、複雑な成形には不適であるとのことだった。ここでは主に後者の熱可塑性樹脂を含浸させた繊維材料の成形方法について紹介された。具体的にはダイヤフラム成形、プレス成形、折り紙、Welding、圧縮成形、ハイブリッド成形を図解で分かりやすく紹介され、これらの成形を経て、航空機の胴体のほか、スポーツシューズの裏地、スノーボードや競技自転車など激しいスポーツで使われるヘルメットにも適用されているとのことだった。どの成形方法を適用するかはコストも関係しているようで、例えば、コストを最小にするような成形方法の提案などORの手法による提案ができるのではと感じた。
三人目の講演者の伊藤 弘道 氏(金城学院大学 消費生活科学研究所)は、航空機の予防保全におけるORモデルについて解説された。航空機の部品点数は約300万点になり、これらの部品はエンジンや空気の乱流による振動、離着陸の衝撃による荷重を受け、クラックなどのダメージが発生・成長するため、これらの疲労限度を考慮した予防保全が不可欠である。これらすべての部品の点検と保全を毎回行うことは不可能なため、空港できる操縦系統や動力系統の簡単な点検などの予防保全(Aチェック、Bチェック)、ハブ空港などで航空機機体の一部を分解し、点検する予防保全(Cチェック)、機体を完全に分解してオーバーホールする予防保全(Dチェック)の4種類に分けて予防保全が行われる。この4種類の予防保全方策にオペレーションズ・リサーチの保全方策理論の一つであるImperfect Maintenance Modelを適用し、コストを最小にする4種類の最適な保全時期について解説された。また、運用による収益と航空機の売却益による「利益」と予防保全費用や事後保全費用などの「損失」を考慮した航空機の運用打ち切り方策、さらに機体に発生するクラックや腐食などを検査で見つけ、ある一定レベルを越えた場合に保全する方策についても事例を挙げながら解説された。ORの有用性を感じる講演であった。
今回は様々な分野の専門家が、それぞれの立場で問題点を見つけ、それを解決するための技術について紹介をしていただいたが、他分野の技術を知ることで、新たな問題を見つけ、解決法を探求することの重要性を再認識する講演であった。
ルポ担当:岐阜市立女子短期大学 木村 充位