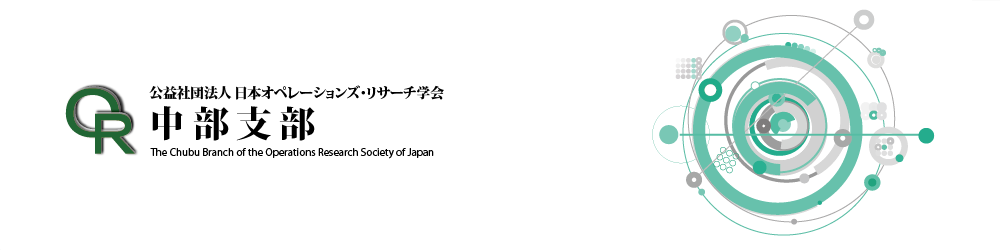SSOR中部支部2019
合宿形式の若手育成プログラム
日時:2019年8月29(木)-30日(金)
場所:愛知県蒲郡市公立学校共済組合 蒲郡保養所 蒲郡荘
〒443-0034 愛知県蒲郡市港町21-4 0533-68-2188
http://www.gamagoriso.com/
OR学会中部支部では,若手育成プログラムの一環として,前年度に引き続き合宿形式(1泊2日)の研究集会を開催します.若手の皆さん,この機会に関する日頃の研究成果のみならず卒論・修論・博論の中間発表をして,OR学会にも研究仲間を作りませんか? 発表時間は2種類あり,質疑応答含め,ショートは10分,ロングは20分を予定しています.
この研究集会では,若手の皆さんの発表会に加え,懇親会,参加教員によるチュートリアル講演を企画しています.
多くの方のご参加を目指し,発表者の参加費をリーゾナブルに設定しました.
どうぞ奮ってご参加ください.
発表者資格について
本イベントは,日本OR学会ならびに中部支部の支援を受けているため,発表者は,
①平成生まれ,または,学籍があること,
②本人または指導教員が日本OR学会会員であること.
のいずれもが必要です.
参加登録方法
下記,リンクより申し込んでください.
入力項目は,氏名,所属,発表題目,発表概要(200文字程度)などです.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfuuU4PuKQghhyYuK5GO4awCtMzDMzfZte_V-6JNucMeN8MNg/viewform?c=0&w=1
登録期限
2019年7月31日(水)
発表・予稿について
発表はパワーポイントなどで実施していただきます.予稿集には,題目と概要のみ掲載します.配布資料などがあれば,発表者ご本人に会場にご持参いただくことになります.
プログラムについて
こちらの支部WEBにて,8月初旬に公開するとともに参加者に連絡します.
参加費について
参加費は以下の通りです.当日,現金にて参加費をお支払い下さい.なお,発表予定のない若手の方は,一般扱いとなります.ご留意ください.
発表者 6,000円(懇親会費・宿泊費・朝食費を含める)
一般 11,000円(同上)
懇親会のみ 5,000円
聴講のみ 無料