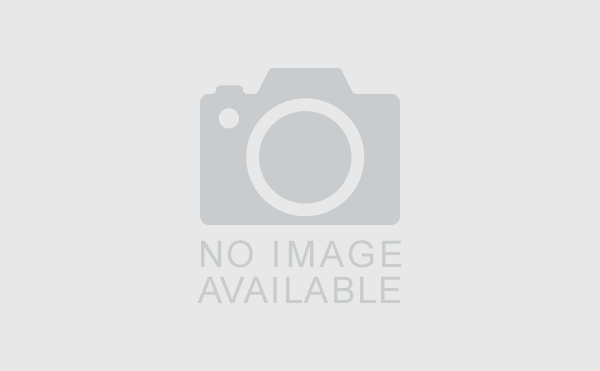2025年度 関西支部シンポジウム(2025/12/15)のご案内
テーマ:DC最適化の新展開
日 時:2025年12月15日(月) 13:15~17:15(13:00受付開始)
会 場:大阪公立大学 文化交流センター ホール(https://www.omu.ac.jp/bunkakouryu-center/access/)
形 態:対面形式(オンライン配信も用意します)
参加費:無料
【12月5日(金)まで】 シンポジウム(および懇親会)の参加登録はこちら
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdBxhZ0zWxs-g398j7Kw6-i9FXCpjKlmNyPugPGr0wPH_GBdg/viewform?usp=header
※ 現地聴講者が多数の場合は制限させていただくことがあります。
※ 会場に余裕がある場合は当日参加も受け付けます。
趣旨:
DC (Difference of Convex) 最適化問題 (またはDC計画問題) は二つの凸関数の差で表現された関数 (DC関数) を含む最適化問題です。近年になって、特に機械学習、信号処理、制御工学などの分野で、DC最適化が着目されています。その理由として、非凸な最適化問題を表現できる、効率的なアルゴリズムを簡単に実装できる、凸解析の技術が利用できることなどが考えられます。一方で、大域的最適化の分野はDC最適化問題を厳密かつ効率的に解く試みが研究されています。そこで、本シンポジウムでは、さまざまな領域で活躍されいる研究者をお招きしてDC最適化に関する最新の研究をご講演していただきます。本シンポジウムの開催を通じたDC最適化に関する横断的な情報交換や研究交流は、非線形計画法の理論およびその応用分野の発展に寄与できると期待されます。
プログラム:
13:15 – 13:20 開会挨拶
13:20 – 14:10 DC正則化付き最適化問題に対する近接写像に基づく数値計算アルゴリズム
中山 舜民 先生(東京理科大学)
機械学習や統計学などの多くの分野で、LASSOなどの非平滑な正則化付き最適化問題がよく扱われるようになってきた。LASSOは線形回帰の最小二乗問題にL1ノルムを罰則に加えた正則化付き最適化問題である。この問題を解くための最適化手法として、近接写像と最急降下法を組み合わせた近接勾配法や、(重み付き)近接写像とニュートン法を組み合わせたニュートン型近接勾配法が知られている。近年、正則化として非凸な関数がよく扱われ、実用的な非凸な正則化はDC関数である。本講演では、DC関数で表せる非凸な正則化付き最適化問題に対して、近接写像の基づく最適化手法の紹介し、その性質について解説する。
14:20 – 15:10 計測データ解析における近接分離型DC最適化の可能性
小野 峻佑 先生(東京科学大学)
計測対象の高度化・複雑化が進む現代の先端科学/工学の要請に応えるため、様々な劣化を伴う計測データから背後の信号情報を解析する技術ー計測データ解析ーの重要性が高まっている。これまで計測データ解析では、その汎用性と計算効率性から、凸最適化技術の一つである近接分離アルゴリズムが広く用いられてきた。しかし実計測に伴う諸課題では、 凸最適化の範疇では近似的にしかモデリングできないスパース性や低ランク性といった性質を、厳密に扱わなければならないケースも多い。このギャップを埋めるには、柔軟な非凸モデリングと近接分離アルゴリズムの汎用性・計算効率性を兼ね備えた新たな最適化技術が不可欠であり、その有力な候補として「近接分離型DCアルゴリズム」が位置づけられる。本講演では、まず、計測データ解析と最適化技術に関する背景知識を解説し、続いて、現時点で計測データ解析への応用が進みつつある代表的なアルゴリズムとして、近接線形化DCアルゴリズム、一般化二重近接勾配DCアルゴリズム、近接交互方向乗数法型DCアルゴリズムを紹介する。さらに、リモートセンシングデータ解析における代表的なタスクである異常検知やミクセル分解の事例を通じて、近接分離型DCアルゴリズムの有効性と今後の発展可能性を示す。
15:20 – 16:10 DC計画による非負システムの最適化
立命館大学 趙 成岩 先生
本研究では,DC計画を用い,非負システムの状態、入力や出力行列設計のため新たな最適制御方法を構築する.一般的な線形システム方法では,フィードバック制御が線形関係のため,非線形が存在することで対応が困難となる.その一方で,単純な数理非線形最適化問題をまとめ,大規模な問題からの計算量の爆発があり,最適解への収束表現も保証できない.DC計画において,変数が非負の範囲に制約され,2つ非負非線形関数の差として定義されるDC関数に取り扱う数理計画を基盤とする制御法の構築を目指し,大規模な問題に対する最適解への収束表現と大規模な問題への計算効率が改善できる.理論研究成果に踏まえ,大規模な複雑系システムに対する数理的な解明・制御方法の構築が可能となる.実際の電力・交通などの複雑系は非線形性を持つため,非線形に取り組むことは避けられない課題であり,最適制御への収束表現と大規模な問題への計算効率が注目されている.
16:20 – 17:10 標準DC2次計画問題に対する大域的最適化アルゴリズムについて
新潟大学 山田 修司 先生
本発表では,標準DC2次計画問題に対する大域的最適化アルゴリズムを紹介する。任意の2階連続微分可能関数はDC関数に変換可能であり,また任意の連続関数はDC関数列の極限として表現できるため,多くの数理計画問題がDC計画問題に変換または近似可能であることが知られている。この背景から,標準DC2次計画問題は大域的最適化の分野で重要な研究対象問題の一つとして位置づけられている。本発表では,FJ点(Fritz-John条件を満たす点)の列挙法と分枝限定法を組み合わせたアルゴリズムを解説し,ダム建設におけるスケジュール最適化や稲作工程の最適化といった応用事例を紹介する。
17:10 – 17:15 閉会挨拶
問合せ先:
大阪公立大学大学院情報学研究科 楠木 祥文(シンポジウム実行委員長)
E-mail:yoshifumi.kusunoki(at)omu.ac.jp
ただし,(at) を @ に変えて送信してください.